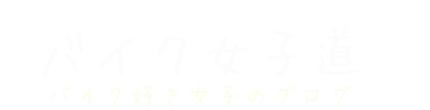カフェレーサーはどこから始まった?
カフェレーサーという名前は、1960年代のイギリス・ロンドンにある「Ace Café(エースカフェ)」が発祥とされています。そこに集まっていた若者たち、いわゆる“ロッカーズ”が公道でレースのように走り、自分たちのバイクを速く・軽く仕上げるカスタム文化が生まれたんですね。
このスタイルが「カフェレーサー」と呼ばれるようになった背景には、「カフェから他の店まで音楽1曲分で走りきる」という遊び心があったとも言われています。バイクと音楽、そして自由な走り。そんな要素が混ざり合いながら広がっていったスタイルです。
日本には1970年代ごろから広まりました。特にヤマハSRやホンダGBなど、シンプルな構造の車両がベースとして人気を集め、現在に至るまでその文化が続いています。
速さも映える、カフェレーサーのデザイン
カフェレーサーと聞くと、多くの人が独特なフォルムを思い浮かべるでしょう。低いセパレートハンドル、長く細い燃料タンク、そしてリアが上がったシングルシート。この流れるようなシルエットが、どこかレーシーで美しく見えるんです。
デザインのルーツは、当時のレーサー仕様のバイクにあります。できるだけパーツをそぎ落として、軽く速く仕上げるという思想。外装も必要最小限にとどめ、実用性よりも美しさや一体感を重視したスタイルが目立ちます。
現代では、ネオクラシックとしての価値も加わり、レトロとモダンが共存するデザインとして評価される場面も増えました。見た目の雰囲気が好みでカフェスタイルに惹かれるという人も少なくありません。
広がるカスタムと現代の潮流
カフェレーサーは、自分らしくカスタムしやすいバイクとしても知られています。昔からの代表的なベース車両といえば、ヤマハSR400やホンダGB250クラブマンなどが挙げられますね。構造がシンプルで、パーツの種類も多いため、初心者でも手を入れやすいという魅力があります。
セパレートハンドルやバックステップ、細身のガンファイターシートなど、好みに合わせて自由にカスタムできるのが面白いところ。パーツを少しずつ変えていくだけでも、「自分だけの一台」に近づける実感があるでしょう。
近年は、メーカー純正でカフェスタイルに仕上げられたモデルも登場しています。たとえば、トライアンフのスラクストンRSやカワサキのW800カフェなどがその代表例。クラシックな見た目を持ちながら、現代的な装備と走行性能も備えており、完成度の高さが評価されています。
カスタムで仕上げるか、完成車をベースに手を加えるか。選択肢が広がっている今だからこそ、自分のスタイルに合った楽しみ方を見つけてみるのもいいかもしれません。